「ずたぼろ赤猫ものがたり」風スペシャルブックレット
ミニキャラアイコン
※タップ(クリック)して画像を表示。長押しでダウンロードください。 ※画像データの再配布等を禁じます。
アニメイトタイムズ リレーインタビュー
各話放送記念イラスト
各話おすすめコメント
放送カウントダウンイラスト
原作・とびらの先生書き下ろし
ショートストーリー
ショートストーリー
1話でお姉ちゃん退場かぁ…って思った……? みなさーーん!!!アナスタジア!!生きてますよーーーー!!!!(大声) ずっとずっと温め続けたこの気持ち、みんなに伝わるといいな…! 見どころはなんといっても、ついに明かされるアナスタジアの謎…!彼女の波瀾万丈な人生を是非一緒に追いかけていただきたいです。 物語もいよいよクライマックス。絶対にお見逃しなく!!
アナスタジアのお当番回です! あの時何が起こって今までどうしていたのか……。 アナスタジアがマリーに対してどう思っていたのか、 色々な人達の思惑が見えると思います。 衣装変えが多かったので、色の調整が大変でした……。 見どころたくさんの回です!楽しんでいただけると嬉しいです!
くっついては離れてくっついては離れて忙しいマリーとキュロス。 たった一つのすれ違いから始まって、揺れる感情、コンプレックス。 キュロスも大変だね……。 また笑って過ごせる日々が戻ればいいですが……どうなることやら……10話お楽しみに!
欲しいものを欲しいということさえ勇気のいるマリーの心情にリンクして描かれた、時間帯の違う景色の色を一緒に感じて頂ければ嬉しいです。
姉アナスタジアの事故の核心に迫る出来事と、謎めいた展開にマリーの心が揺れる!! そんな回です。
ダマスクローズの髪飾り、母を縁取るフリージア、そして第9話では、亡くなった姉に手向ける白いユリの花束……、象徴的に使われる花にも注目です。 後半に進むにつれて伏線が回収され始め、さらに物語に引き込まれます!
デート後半戦の8話です! マリーとキュロスの距離がまた一歩前進します。 見どころは何といっても『夜明け』のシーン。 演技、色合い、撮影、音楽 とても綺麗に仕上がっています。 ぜひ観てください!
第8話は見ていて笑顔になれる楽しく可愛らしいシーンや、思いやりあふれるシーンがたくさん見られます。 いろんなキャラクターの優しさが垣間見えるお話だと感じました。 映像と共に、ミュージシャンの方のエモーショナルな表現も素晴らしいので、是非お楽しみいただけたら嬉しいです!
7話はミステリー要素が加速します! ラブ、コメディ、アクション、さまざまな顔を持つ本作ですが、謎解き部分もとんでもなく面白い! あらためて、とびらの先生の引き出しの多さに驚かされました。ぜひお見逃しなく!
ここまでマリーが周囲から認められて自立していく様が描かれてきてきました。 第7話ではシャデラン家の奇妙なところ、謎がミオの活躍によって見えてくるのが趣向が違って面白く、ぜひその辺に注目して見てほしい!
リュー・リューとマリー2人の距離が一気に近づき、マリーの心がやわらかく解放される瞬間がたまらないと思います。 スタッフの方々からも「楽しみにしていたシーン」と言われとても緊張しつつ臨んだ収録でしたが、アフレコ後はますますマリー(と本村さん♡)のことが愛おしくなりました。 観たら思わず泣いてしまうかも…?!ぜひお楽しみくださいませ♪
今話、二人が互いにより惹かれ合っていく様子はとても良かったです。 また、マリーが伯爵家に家族として受け入れられていく様子には心も温かくなります。 あとブルーベリータルト。 ラストシーンの衝撃は凄かったです。
ルイフォンの見せ場のようでいて、彼がある種の邪魔者のように登場することによって、二人の仲が周囲にも二人にとっても明確なものになる回です。そして作品が変わったのではと思うほどの、美しい二人による美しい戦いも素晴らしいクオリティ!更にはルイフォンを通して、キュロスの素や過去も知ることができますよ!つまり、やっぱりルイフォンの手柄がたくさんの見せ場回ですね!!お楽しみに!!!
ルイフォン王子、顔がいい!悪役ムーブしてても顔がいい! 対決シーンのアクションのよさ!剣技からの拳闘!なんてかっこいい! 吹っ飛ばされるとこもいい!イケメンがとっちめられる栄養素の美味しさよ!顔が!いい!
本来主従関係ではあるのですが、マリーとミオが、姉妹のように、友達のようになっていく姿が描かれていてとても微笑ましいです。 前に出て引っ張るのではなくて、そっと横に寄り添い、そっと背中を押す。そんなミオの立場を踏まえた優しさと愛情がたくさん見えるお話になっています! 力持ちで、食べるのが大好きで、そしてさらにマリーという大好きな方が増えて、ミオは幸せですー!
第4話は物語の転換点にもなるたくさんのイベントがありましたが、やはり印象的なのはルイフォン王子の登場ですね! あと、ミオ。とにかくミオがずっと素敵! 実はうなぎ、ミオのファンなんですよね。
第3話では、グラナド城の日常を切り盛りしてくれている、頼もしい仲間たちが登場します。 マリーとキュロスがいかに周りから愛され支えられているかが分かる、素敵な話数なんです! あまあましりとりコーナーも見どころかな!笑
アニメ化おめでとうございます! さあ、皆様、ついに第3話でございます!第3話からは、登場⼈物が⼀気に増えます! ずたぼろ令嬢はどのキャラクターも魅⼒的ですが、サブキャラでは私はトッポが好きです! 第3話は「きぃぃぃぃ!」と視聴者は思ってしまうシーンがいくつかあるのですが、マリーは優しく素直な性格なので「きぃぃぃぃ!」となっていないのが、彼⼥らしくて素敵です。 そして⾒どころ……ラブシーンもございます! もう⽢くて⽢くて「君たち、私が吐いた砂糖差し上げましょうか?」と例のシーンで⾔いたくなりました!どのシーンかはぜひ観てご確認ください! とっても⾯⽩くて胸きゅんなシンデレラストーリー、ご堪能あれ!
第2話は、マリーがミオに夢から起こされて、焦っているシーンがマリーの可愛らしさを感じられて好きです! エンディングでは楽曲と共に、健気なマリーの姿が見れて嬉しいです。
天津飯大郎です。 こちら2話では自分を大事に出来ないマリーと、大事にしたいキュロスのやり取りを見て欲しいです!すれ違い勘違いがたくさんあった出会いだからこそ、二人を応援したくなること請け合い! 男性でもめちゃくちゃのめり込めます!マリー!キュロス!幸せになって!
第1話の見どころは、ずばり、全部!です!! この原作再現度の高さ!マリーもキュロスも、僕たち私たちがずっと思い描いてきたイメージそのままに、絵が付き色が付き動きも付いて声まで付いて来た。 2話以降への期待も煽られるというもの。 特に私は、ずたぼろマリーが母親に理不尽ビンタ喰らったときの「ゔっ」が大好きですね。 何度もリピートして聴いてしまいます。 本村玲奈さんの悲鳴が、本当に痛そうで可哀想で……可愛い。
自信が持てないマリーの姿に心が苦しくなったり、 時々見せる素直な一面は微笑ましさを感じたり… 健気な姿に惹き込まれます。 マリーが少しずつ光輝く瞬間が増えていくのを共に見届けていきたいと思います。
午後のグラナド城。柔らかな陽光が差し込む、リラクゼーションフロア。 大きな机の上に、わたしはカードを並べていた。時々カードをめくっては、そこに書かれた文字を読み上げる。 「ラウール伯爵……七十歳、白髪青目カイゼル髭、鼻の下にホクロ。口癖は『実に素晴らしい』……」 ――と、その時。 「やあキュロス君! 元気してるかい!!」 大きな音、そして声と共に突然、背後の扉が開かれた。びっくりして振り返ると、扉のそばに目の覚めるような銀髪の美青年が立っている。ここディルツ王国の第三王子にして騎士団長、ルイフォン・サンダルキア・ディルツ殿下だ。そして、キュロス様の十年来の親友でもある。わたしは慌てて椅子から立ち上がり、一礼した。 「ル、ルイフォン様、いらっしゃいませ! すみません今わたし、一人しかいなくて、キュロス様はお仕事にお出かけでしてっ……!」 「うん知ってる。夕方に帰ってくるんだろ? それまで待たせてもらうよ」 ルイフォン様はそう言って、つかつかと遠慮なく部屋に入ってくる。そしてわたしの手元、机に広げたカードを見下ろすと、なぜかニヤリと笑った。 「これって、暗記用のカード? 表が人名で、裏に個人の情報を書いたやつ」 「は、はい。婚約式本番では多くの王侯貴族とお会いするでしょう。その時までに、頭に入れておかなくちゃって……分厚い人物史図録を持ち歩いていたら、キュロス様が作ってくださったんです」 ルイフォン様の細い眉がピクリと動く。少し気になったけど、わたしはそのまま続けた。 「これを使えば覚えやすいぞって。キュロス様って、すごいですよね。貴族の責務や貿易のお仕事だけでなく、座学にも優秀であられたなんて。学生時代の彼が見てみたかったわ。きっと、さぞかし優秀だったんでしょうね」 「ふっ――はははっ!」 突然、ルイフォン様が高らかに笑い始めた。 「残念! キュロス君、暗記問題は苦手なほうだったよ」 「え……そうなんですか? でもこの勉強法は本当よく出来ていて……」 「それは僕のアイディア。苦労していた彼に、この僕がコツを教えたんだよ」 「まあ、そうだったのですか」 わたしは心の底から驚きの声を上げた。 意外だわ。何でも知っているキュロス様にもそんな時代があったなんて。 「ルイフォン様の『ご学友』は、わたしの知るキュロス様と別人みたいですね」 わたしとしては本当に、何の他意も悪意もない発言だった。だけどルイフォン様は表情を曇らせた。何か、気分を害してしまったらしい。 「それって――今のキュロス君は昔と違う、自分は僕よりもキュロス君のことをよく知っているって言いたいのかい、マリーちゃん?」 「えっ!? い、いいえ全くそのようなことは――」 わたしはブンブン首を振ったけど、ルイフォン様の機嫌は直らないまま。わたしは慌てて弁解しようとしたけれど、そもそもルイフォン様が何に怒っているのかがわからない。わたし、そんなに変な発言をしたかしら? ただ昔話をしていただけなのに。 えっと……これは……? 「あの……ルイフォン様。もしかしてその――わたしに張り合おうとしていらっしゃいますか? 自分のほうがキュロス様と仲がいい、みたいなことで……」 「え? そ……。や…………。………………」 ルイフォン様の顔がみるみる赤くなっていく。あ、やっぱりそういうこと? わたしは口元を手で隠した。思わず笑ってしまいそうだったから。だけどどうやら、目を細めていたのは隠せていなかったらしい。ルイフォン様はわたしの顔を見て、ますます顔を赤くし、拳を握ってブルブル震えた。 「ち、違――違うっ! なんだそれ、そんなわけないだろ!?」 ルイフォン様は叫んだ。 「別に、何ら他意の無いことだ。そう、当たり前なんだよ。女性の前だと、男はつい虚勢を張ってしまうからね。男同士でいる時とは別の顔をするものさ」 今度はわたしのコメカミがピクッと跳ねる。 ……なによ、それ。それじゃあわたしの知るキュロス様は真実の彼ではない、と? たしかにルイフォン様のおっしゃることも一理あるとは思うけど、なんだか……悔しい、というか、反論したくなると言うか……。 そんなわたしの心境など、ルイフォン様はお見通しらしい。腕を組んで、わたしの顔を覗き込むみたいに身を屈める。 「不満なら、反論したまえよ奥様。そういえば以前、『キュロス様の良いところをお話ししましょう』とか言ってたしね」 「えっ……」 「キュロス君の良いところ、僕も知らないことをたくさん知っているんだろう。ほら話してごらん。キュロス君の何がすごい、どこが好きって」 「え……え、ええと。それはその――」 「ほら言ってごらんよ、さあさあ」 「う、うっ……ぐぐぐっ……!」 わたしは唇を震わせた。こういうことを改めて言うのは悶絶するほど照れくさい――けれど、黙り込んでしまったら、ルイフォン様はさらに煽ってくるだろう。「そうかそうかキュロス君の良いところなんて何もないってことだねー」とか。 いやだ。そんなの悔しい。ここは……退けない! 負けるわけにはいかないわ……! わたしはグッと拳を握って、息を吸い込み、胸を張った。 「では、お話しします。わたしは彼を、すべてにおいて最高の男性だと思っていますから」 「王家に次ぐ最高位の貴族令息で、国一番の大富豪だもんね」 「そういったことではなくてっ。もちろんルイフォン様もご存じのことでしょうが、彼自身が素敵な男性です。見た目も性格も!」 「なるほど、具体的には?」 突っ込まれて息を呑む。ルイフォン様は目を細めて、わたしをニヤニヤと見下ろしていた。あ、これ、罠にかけられたかも――でも、辞めるわけにはいかない。わたしはさらに堂々と胸を張った。 「一番好きなのは、目です。透き通った緑色で。それだけでも綺麗なのに、さらに彼の感情で潤んだ時には、エメラルドよりも煌めいて……」 「肌の色と同じくらい、不気味だって言われがちな要素だけどね」 「そんなことは決して――ああそうだわ、キュロス様の素敵な所、もうひとつ。自分の容姿を卑下しないところです」 「……自意識過剰だって言いたい?」 「とんでもない! 自分に自信を持つことは良いことだわ。それにキュロス様が堂々としてらっしゃるのは、母君――リュー・リュー様を否定したくないからでしょう?」 わたしの言葉に、ルイフォン様はニヤニヤ笑いをピタリと止めた。 そう――かつて、わたしは少し、不思議に思ったの。キュロス様ってどうしてこんなにも堂々としていられるのだろうって。彼はディルツ人ではあるけれど、大抵イプサンドロスの伝統礼装を着ている。自分のルーツはここにある、恥じ入ることなど何もない――母を貶めたいならば、まず俺に言えと喧伝するかのように……。 ルイフォン様は「フン」と鼻を鳴らした。 「なるほど、いかにもマリーちゃんらしい気付きだね。確かに、彼は家族思いの男だよ」 「優しいだけでなく、力もたいへんお強い方ですよね。剣術披露会では騎士団長のルイフォン様にも勝利したし……」 「あれは剣術勝負じゃない、殴り合いだろ!? ほんとだったら先に剣を落とした時点で僕の勝ちだし!」 それはその通りだけども、それで決着とせずトドメの一撃を入れようとしたのも、お互い剣を失くしたあと殴りかかったのもルイフォン様からでは? 「僕から言わせてもらえば、キュロス君は本当に負けず嫌いで血の気の多い男だよ。座学の成績だって、僕に負けたら躍起になって勉強していたからね」 なぜか嬉しそうに言うルイフォン様。わたしはこっそり笑った。だって、全く同じことをキュロス様が言うのを聞いたことがあったから。ルイフォンは負けず嫌いだ、俺に負けたら躍起になって勉強して――って。 「仕事でもね。キュロス君の現在の爵位、経済力は、本人の努力によるものだ」 「たしかに、彼の商才については、わたしが評価をするのもおこがましいです」 「いいや遠慮なく褒めればいいよ。巷で言われる悪評、キュロス君が気難しいとか強欲だとかっていうのはただの誤解と嫉妬だ。彼のそばにいる人間は、みんな真実の彼を分かっている。キュロス君の商才、いや人格を評価しないやつなどいないよ」 わたしはウンウン頷き、手を叩いた。 「ええ、ええ、おっしゃる通り。わたしもルイフォン様も、キュロス様が大好きですよね!」 「ああその通り、君も僕もキュロス君が――」 次の瞬間、さっきまで調子よく喋っていたルイフォン様の動きがピタリと止まった。さらにその顔がみるみる赤くなっていく。どうしたのかしら……と思ったその時、わたしの後ろから、男性の低い声がした。 「……ふたりとも……いったい何の話をしているんだ」 振り返ると、そこに立っていたのは長身に黒髪、褐色の肌と、緑の目をした美丈夫だった。 扉のそばに立ち、なぜか頭痛を抑えるようなしぐさをしている。わたしは顔を輝かせた。 「キュロス様! お帰りなさいませ!」 「ああ……うん。ただいま」 「御覧の通り、ルイフォン様がお見えです。今ちょうど、ふたりでキュロス様のお話をしていたんですよ」 キュロス様は、凛々しい眉を困ったように垂れさせて、なんとも居心地悪そうな顔をした。 「うん、それは……聞こえていた。だから今、反応に困っている」 「あっ、ご、ごめんなさい。陰口を言っていたわけでは決して。ただ話の流れで、キュロス様の良いところを語り合う会というか、張り合う会と言うか。ルイフォン様とわたし、どちらがよりキュロス様のことを好きかを競うみたいに――」 「競うって何だよ!! 張り合ってない、いやそもそもそんな話をしていないっ!」 突然、大きな声で叫ぶルイフォン様。 え……でも、間違いなくわたし達、そんな話をしていたし。キュロス様も聞いてしまったからこその反応だろうし……。 ルイフォン様はわたし達の白けた視線を受け、プイと顔を逸らし、背を向ける。あらら、本格的に拗ねてしまった。 キュロス様はため息をつきながら、ルイフォン様の背後に歩み寄っていく。 「まったく。妙な噂話は、俺の耳に届かんようにやってくれ。マリーに言われるなら嬉しいばかりだが、おまえからだと、なんというか――反応に困る」 「心配しなくても、二度と言わないよっ。いや、言ってない。そんな話してないからな僕は!」 「はいはい、まあいいさ。それよりルイフォン、何の用事だ。ただ遊びに来ただけなら、今日はもう帰ってくれ」 「あ、ああ……じゃあ」 「今日の俺は忙しい。俺がおまえを評価しているところ、おまえの良いところについて、マリーと語り合う時間が必要だ」 「――帰るっ! 二度と来るか!!」 ルイフォン様は今度こそ、床が震えるほど大きな声で絶叫した。 大股で部屋を出て行く王子様に、キュロス様が大笑いする。わたしもクスクス笑いながらも、隣に立つキュロス様を見上げた。 「……良かったのですか? ルイフォン様、きっとご用事があって来られたのでしょうに」 「ないない。もしあるならば、恥を忍んででもちゃんと居残ったさ。案外、仕事には真面目な男だからな」 「…………ルイフォン様のこと、よくご存じなんですね?」 わたしが問うと、ニヤリと笑うキュロス様。それからわたしの肩を抱き寄せ、自分の胸に閉じ込める。そうしてわたしを拘束したまま、静かに、甘い声で囁いた。 「――では、このままミオを呼ぼうか。そして俺とミオが語り合うのを聞いてくれ。マリーの可愛いところ、愛しているところを延々と挙げ続けるからな」 「えっ!?」 「いやあちょうど良かった、仕事で留守にしがちなぶん、言いたいことが溜まっていたんだ。君がいかに綺麗で可愛くて、俺の胸をときめかせる存在か、君の姿を見るたびに、俺が何を考えているか――出尽くすまで、どれだけ時間がかかるかわからない。だが――」 囁きながら、わたしの体を拘束するキュロス様。長い腕の力を強くして。 「逃がさないぞ。夜が明けるまでずっと、聞かせてやる」 ……う……うう。 「……ふぁい……」 わたしは何もかも諦めて、赤面しながらも頷くしかないのだった。
「マリー、ただいまっ!」 ――という、朗らかな声と共に、キュロス様は何か大きな物を手渡してきた。 「これは君へのお土産だ。包みを開けて見てくれ」 「あ……ありがとうございます」 わたしはお礼を言いながらも、正直少し、委縮していた。 キュロス様からお土産をいただくのはこれが初めてではない。しかし決まってそれらは超高級品、目がくらむような宝石やドレスだった。今度は一体、どんな物を贈られてしまったのだろうか……。 恐る恐る、震える指で包みを開く。 するとそこには意外にも、薄い布が一枚入っているだけだった。 「マリー、気晴らしに裁縫をしたいと言っていただろう?」 わたしは笑顔で頷いた。 すごく綺麗で、肌触りの良い布だった。 拡げてみると、大人の身長より長く、全身包まれそうな幅もある。所々に入った金色の刺繍も上品で、これなら色々と作れそうだわ。わたしには服作りの技術もセンスもないけれど、簡素な寝間着くらいなら縫えるのだ。チュニックと、農作業用の手袋、それから髪留めのシュシュをいくつか……靴下なんかもいいわね。 「ありがとうございます。キュロス様にも何か、お作りしましょうか。簡単な物で良ければですけど」 「それは嬉しい。そのイプスシルクに金糸の刺繍なら、素晴らしいものが出来そうだ」 わたしはピタリと動きを止めた。 …………イプサンドロス製の絹布に、金糸の刺繍……って。 そういえばこの光沢、今まで見たことないほど美しく、厚みがあるのに透き通って見えるほどに煌めいてて……。 これってもしかしてグラナド商会の取扱い品でも最高級の……? だとしたら、これ一枚で家族が一か月食べていける金額で……。 蒼白になって震えるわたし。キュロス様はそれには気付かなかったのか、上機嫌で城内へと入っていく。 「マリーの手縫いかあ。楽しみだなあ」 …………えっと。わたし……この布に、ハサミを入れるの……!? わたしはキラキラ光る絹布を抱え、呆然とその場に立ち尽くしたのだった……。 「――というわけで。たくさんの綿を調達したいの!」 と、わたしが高らかに宣言すると、侍女のミオはいつも通りの無表情から、呆れたような半眼になった。 ティーテーブルに茶菓子を並べながら、静かな声で尋ねてくる。 「なにが、というわけで、なのかよくわかりませんが。その布で、ぬいぐるみでも作ることにしたのでしょうか?」 わたしは首を振った。 「ううん、ぬいぐるみじゃなくて、抱き枕を」 紅茶を注ぐ、ミオの動きが一瞬ぴたりと止まった気がした。 ん? どうしたのかしら? わたしが問うより早く、ミオはすぐに作業を再開する。 「………………なぜ抱き枕?」 「だって、この布から靴下なんて、とてもじゃないけど作れる気がしないもの。抱き枕なら色んな意味でちょうどいいから」 「……色んな意味、ですか。そうですか……」 ますます顔面から表情を失うミオ。 なんだか、変な反応。もしかして、キュロス様の贈り物に難癖をつけたと思われたかしら? わたしは慌てて弁明した。 「キュロス様からの贈り物はとても嬉しかったの。だから、絶対に失敗しない物を作りたいのよ」 そう――最初は靴下や手袋など、小物を色々作ろうと考えていた。だけどこんなにも高価で貴重な絹布に、ハサミを入れるのはもちろん、針を持つ手も震えてきそうで。 もともと裁縫が得意ではないわたしが、確実にちゃんと作れて、彼に喜んでもらえるもの――。 絹布を抱いたまま、わたしは一晩中考えて考えて……いつの間にか眠りに落ちた。そしてふと目を覚ました時、頬に触れる絹の感触に蕩けた。 そして思いついたのだ。抱き枕を作ろう、と。 抱き枕ならひたすら端を縫い合わせるだけで完成するし、絹の肌触りを存分に活かせる。 うん、我ながら素晴らしいアイディアじゃない!? そうしてわたしは意気揚々、朝一番でミオの顔を見るなり綿を所望したのだった。 ――という経緯を遡って話すと、ミオは「なるほど」と言いながらも、なんとも複雑な顔をした。 「……まあ、いいんじゃないでしょうか。変な意味が無いのであれば」 「? どういうこと?」 「いいえなんでも」 ミオは何故かわたしから目をそらした。 「そういうことならば、承知いたしました。綿のほうは今すぐ、城内にあるものをお持ちいたします」 「ありがとう! 綿の量は、出来上がりの大きさによるわよね。抱き枕って、どのくらいがちょうどいいのかしら」 「……既製の物がどうであれ、旦那様に贈られるならば大きめの――マリー様の背丈ほどが、ちょうどよろしいかと」 「なるほど、キュロス様は体が大きいものね」 「……………………。」 相変わらず、ミオはわたしと目を合わせてくれない。 「あっそうだ、ついでに、絹用の染粉をもらえない?」 「……抱き枕を染めるおつもりですか?」 「ええ。キュロス様の好きな色って何色かしら」 「通常ならば黒、また差し色には金やエンジがお好みでらっしゃいます。しかし抱き枕であれば、鮮やかな朱色が喜ばれるかと」 「朱色? わたしの髪色くらい?」 「そうですね。もしくはいっそ肌色……もとい明るいベージュでも」 「? えっと……抱いて寝るなら、そういう暖かそうな色味が落ち着く、ということかしら」 「そうですね。いえ違います。申し訳ありません忘れてください」 ミオの様子がなんだかおかしい。 「――さすがにそこまで再現してしまうと、旦那様の人格が疑われてしまいます。色は染めず白のままでいきましょう、そうしてください」 「え、ええ。わかったわ」 「出来上がった物をお渡しになる時は、先ほど私にお話しされた通りの文言で、旦那様に真意をお伝えください。決して含みを持たせたり、“何か知っている”風の口調や表情にならないよう、くれぐれもお気を付けを……」 「? ?? ??」 「大丈夫です、何の問題もありません。忘れてあげてください」 「……いったいなんなの……?」 わたしの問いかけに、ミオは答えてくれなかった。それどころか顔ごと視線を逸らし、綿を取りに部屋を出て行くまで、わたしとは一切口を聞いてくれなくなった。 戻ってきた時には無表情、平坦な口調だけども親切な、いつものミオに戻っていた。時々、ほんの少し――口の端から「くふっ」と、笑い声みたいな息を漏らしていたけれど。 そうして、数日後。 完成した抱き枕を持って、わたしはキュロス様の部屋をお訪ねした。 包み紙で飾るには大きすぎる贈り物――なにせわたしの体と同じくらいある――なので、剥き出しの本体にリボンだけ巻いてお届けする。 「お待たせいたしました。前に頂いた絹布で、わたしが作った物です」 ――と、普通のことを言って差し出したのだが。キュロス様は、その場で石造のように固まった。 ……あれ? 「キュロス様? あの……これ、キュロス様への贈り物……なんですけど……」 「え。あ、ああ。うん。ええと」 なんだかひどくぎこちない仕草で腕を伸ばし、枕を受け取ってくれたキュロス様。表情はギリギリ笑顔の形ではあるけれど、やはり半分、石化している。 「あ――ありがとう。ところでこれは、何という物かな? 大きなクッションだなー」 「抱き枕です。寝苦しい時に、抱きしめたり足の間に挿んで寝ると落ち着くという……」 「ああ、ああはいはい抱き枕。聞いたことはあるぞ。ほぉーこんな形なのか初めて見た。へえほおふうん、なぁるほどなぁ」 感心したような言葉を紡ぎながらも、声には感情が入っていない。彼の態度には明らかに嘘がある。心から喜んでいるとはとても思えなかった。 ……あ……。 わたしは俯いた。 ……そっか。そうよね、やっぱりもっとちゃんとした、手の込んだ物を作るべきだった。ただ袋の形に縫い合わせ綿を入れただけなのに、お手製だなんておこがましい。 いやそもそも、わたしが裁縫をしようと考えたのが間違いだった。わたしはそんなに手先が器用ではない。亡くなった姉、アナスタジアのように、豪華なドレスを仕立てる技術なんてない……なのに。 素晴らしい絹布を、キュロス様からいただいて。嬉しくて、舞い上がってしまった。 これで何かを作れば、きっと喜んでくれるって……馬鹿みたいにはしゃいでしまったの……。 わたしは深々と頭を下げた。 「申し訳ありません、せっかくキュロス様が買ってくださった高価な布を、こんな使い方をしてしまって。あの……処分もお手数でしょうから、わたしが使わせていただきますね」 そう言って、キュロス様のほうへと手を伸ばした。 しかし彼は素早くわたしに背を向けた。まるでわたしに抱き枕を奪われまいと庇うように、本来の用途通りにぎゅうっと抱いて。 「い、いや! 気に入らなかったとかそういうことではないから! ありがとうマリーありがとう、本当に嬉しい、ただ嬉しすぎて言葉がうまく出てこなかっただけなんだ!」 「えっ? ええと、そうだったのですか?」 「うんそう、むしろナイスでベストなタイミングだ。ちょうどこういうのが欲しかった。本当に探していたんだ、洗い替えが欲しいなと――」 「洗い替え? キュロス様さっき、初めて見たって」 「ああその通り、俺は抱き枕なんて持っていない。まして君の背丈ほどの、ちょうどいい感じのサイズの物を特注したりなんかしたことはない。決して、一度も」 「…………ううん?」 「何でもない――とにかくありがとう。本当に嬉しい」 少しまだ汗を垂らしながらも、にっこり笑うキュロス様。 その笑顔は、心からのものだと見て取れる。キュロス様に喜んでもらえて、わたしも嬉しくなって、笑った。 「ふふ。ありがとうございます。さっそく今夜から、使ってくださいね」 「ああ今夜から使――……寝苦しい夜の安眠のために使うことにするよ」 ?? なんだかちょっと、念を押すような言い回しが気になったけど……まあいいか。 わたしはキュロス様に手を振って、踵を返し、廊下を進もうとした。 するとそこへ、キュロス様に声を掛けられた。 「ちょっと待ってくれマリー、部屋に帰る前に、もう少しだけ」 「はい? なんでしょう」 トコトコと小股で戻るわたし。キュロス様はなぜかきょろきょろとあたりを見回し、誰かいないか確認するようなしぐさをした。 そして、腕に仕舞っていた抱き枕をわたしに差し出し、そっと耳元に口を寄せて、 「一度、これを抱きしめておいてくれ。ぎゅうーっと……色々なものが移るように」 後日、このやりとりの一部始終をミオに話して聞かせると、いつも無表情な侍女は、腹を抱えてうずくまってしまった。 …………本当に、なにがなにやら。 もしかして、抱き枕にはわたしの知らない、別の意味でもあるのだろうか。 そうだとしたら……知りたいような、知りたくないような。知ってはいけないような、そんな気がする奇妙な日だった。
目を開くと、そこには美しい顔があった。 褐色の肌、彫の深い顔立ちに、エメラルドのように煌めく瞳。黒のロングテールコートに身を包んだ、我が婚約者、キュロス・グラナド伯爵――。 「おはよう、マリー」 「わ!きゃ!え⁉」 わたしは悲鳴を上げて飛び起きた。 ど、どうしてキュロス様がわたしの寝室に? なにこれ夢?わたしまだ夢の中にいるの? 両頬をペチペチ叩いて覚醒したけれど、やはりベッドサイドにはキュロス様が腰かけていた。わたしを見つめて、柔らかく微笑んでいる。 「お、おはようございますキュロス様。どうしてここに?」 「もちろん、君を起こしに来たんだよ。俺は今日、マリーの執事だからな」 「……は?」 突拍子もない理論展開に、思わず目が点になるわたし。 キュロス様は、太陽のように爽やかな満面の笑みを浮かべて説明を始めた。 「実は今日、ミオもウォルフガングも城を留守にしていてな。君の世話をする人間が誰もいないんだ」 「侍女と執事が、二人とも同時に、ですか?」 「ああ。普段ならお互い示し合わせて休暇を取るのだが、今回ばかりはどうしてもタイミングが重なってしまった」 ……それは、珍しいこともあるものね……? 侍女と執事は、主にとって特別な存在だ。両者にも違いはあるけれど、共通するのは『主専属の、特別な侍従』であること。メイドやフットマンのような雑用はせず、主のスケジュールを管理し、留守中には代役となり、賓客の応対、王侯貴族の公務までサポート。さらには主の精神的な悩みにも寄り添う。 ゆえに二人のうちどちらかは、常に城内にいるのが基本……なのだけど。 「……まあ、そういうこともあるのでしょうね。では今日はわたし、自分のことは自分で」 「マリーのことは俺がやる。つまり今日一日、マリーの執事だ」 「あのそこのところの理論展開が全然さっぱりわからないのですがっ⁉︎」 わたしが叫ぶと、キュロス様はハッハッハッと爽やかに笑った。 「俺は以前、君の侍女役をしたことがあったろう?二人の間にまだ距離があった頃、親しくなるための手段として」 はい、あの時はドキドキしすぎて心臓が壊れるかと思いました――と言いかけた言葉を飲み込む。キュロス様はさらに続けた。 「要するに、あれのやり直しだ。本当に、当時は悪いことをした。まだマリーが俺への警戒心を持っていたのに、勇み足で距離感を詰めてしまい、かえってぎこちなくなってしまった。俺は反省と、後悔をしているんだ」 「……ご理解いただけたならば何よりです……」 「だから今回こそ、程よい距離感を保ちつつ、俺は君の執事になる」 ――いやだからその展開が全然さっぱり本当になんにも理解できません! 「とにかく俺はあの日の続きを、もとい、リベンジがしたい。むやみに体に触れたりなど一切しないから、どうか今日一日は付き合ってくれ――いや。お付き合いを、よろしくお願い申し上げます。お嬢様」 そう言って、キュロス様はわたしの前で紳士の一礼をしてみせた。 それからわたしの髪をひと房つまみ、そっと、口付けて。 「さあ、そろそろベッドから起きてくださいませ。その美しい髪を、わたくしめが整えて差し上げましょう」 「……執事は……お嬢様の髪に、キスをしてはいけないと思います……」 儚く無駄な抵抗をしながら、わたしは全身を赤く染めつつも、とりあえず身を起こしたのだった。 そうして始まった、キュロス様の『一日執事ごっこ』は、驚くほどに本格的だった。 彼には上級貴族の教養があり、大抵のことは何でもできる。つまり城主でありながら、執事役を完璧にこなすこともできるのだ。 彼はまずわたしの髪を完璧に結い上げると、衣装部屋から一着のドレスを持ってきた。 「お嬢様、本日のドレスはこちらをどうぞ、お召しくださいませ」 「……ピンク……それにフワフワのプリンセスドレスですか……?あの、そんなに可愛いのはわたし、似合わないと思うのだけど」 わたしは言った。 男性の平均並みに背が高く、愛嬌の無い顔立ちのわたしには可愛いものなど似合わない――そう、両親から言い聞かされて育ってきた。 そんな呪いの言葉から解き放たれた今も、わたし自身の審美眼でそう思う。 貿易商で、貴婦人の衣装にも目が利くキュロス様が分からないはずがないのだけど……。 しかし彼は首を振り、わたしの手を取って微笑んだ。 「大丈夫。このドレスはラベンダーとシルバーの糸が仕込まれていて、大人の女性にこそよく似合う。シルエットも体型に合い、君の美しさをより際立たせるだろう」 「……。わかりました。ではわたし、挑戦してみます」 わたしが頷くと、キュロス様はニッコリ笑って退室していった。 ひとりで着替え、鏡の前に立ってみる。 ……あ……ほんとだ。確かに、変じゃない。むしろ似合っている……かもしれない。 キュロス様のおっしゃったとおり甘くなりすぎない色味で、わたしの肌や髪の色にも馴染んでいるようだった。 わたしはキュロス様を部屋に呼び戻すと、スカートを広げ、一度くるりと回って見せた。 「すごいわ。キュロス様って、ドレスのセンスまでおありなのですね」 わたしが言うと、クスッと小さく声を漏らし、笑った。 「いいえ、これはお嬢様限定の能力です――俺は毎日、貿易(しごと)先で色んな商品を目にするたび、マリーに似合うだろうかと考えているのだから」 朝食を摂るため食堂に入ると、テーブルには二人分の料理が並べられていた。しかしキュロス様はわたしの背後に立ち、わたしのグラスに飲み物を注ぎ、カトラリーの交換までしてくれる。懇切丁寧な仕事ぶりに、わたしは苦笑して彼を振り向いた。 「キュロス様、給仕は執事ではなく、キッチンメイドの仕事ですよ」 「そうか?まあいいじゃないか、役割分担なんて」 きっと理解しておられたのだろう、キュロス様はしれっとした表情で言う。 ついでにいつの間にかすっかり敬語も取れて、いつもの口調。つまり彼は彼自身の本心として、ごく当たり前のように口にする。 「君の身の回りの世話は、全部俺がする。君の希望を聞き、すべて叶えて見せる。今日はそれが楽しみ――もとい、俺の仕事なんだから」 「ふふ……そうですね。では、忠実なる執事さん、わたしの願いを聞いてくださる?」 彼は一瞬、怪訝そうな顔をしてから、頷いた。 「ええお嬢様、どうぞ、なんなりと」 「わたしひとり、食事をしているのは寂しいわ。隣に座って、一緒に食べてくださらない?」 わたしは笑いながら、自分の隣の椅子を引いて見せた。彼は緑の目を細めると、悪戯っぽい笑みを浮かべた。胸に手を当て、大げさな動きで首を振る。 「いいえお嬢様、ワタクシはしがない侍従。お嬢様と食事を共にするなど恐れ多いことでございます」 「あら、主人のいうことが聞けないの?」 「とんでもありません――ああ、ご命令とあらば仕方がないですね。それでは、失礼いたします」 そう言って、彼はわたしの隣に腰かけた。 ナイフとフォークを手に取って、自分用の食事を食べ始める。一口、口に入れてから、ホッと顔をほころばせた。 「……美味い。実は、ずっと腹が鳴りそうなのを堪えていた」 「でしょうね」 わたしは笑って、彼のカップにお茶を注いだ。 「あなたが執事になって、ずっとわたしの後ろに控えていてくれるのは、心強いけど……それより隣に座ってほしいわ。一緒に、対等な立場で」 湯気の立つカップを彼に差し出し、自分用にもおかわりを注ぐ。そうして同じ温度、同じ量のお茶が入った二人のカップ……わたしは笑って、カップを持ち上げた。 「あなたと同じ時間を過ごしたいの」 「……マリー……」 キュロス様の手が、わたしの髪をひと房つまむ。だけど彼は髪にではなく、わたしの顔に口付けた。小さく音を立て、頬と額に柔らかな唇を押し当てる。それからわたしの顎に指を添え、少し角度を持ち上げて――。 ――と、その時だった。 「旦那様」 背後から、聞きなれた老紳士の声がした。 「――ウォルフガング!」 「なにっ⁉」 キュロス様は悲鳴じみた声を上げ、慌てて背後を振り返る。 「な、なんでウォルフっ……なぜここにいる⁉今日は暇を出したはずだぞっ!」 「ええ、ありがたく朝寝坊をさせていただきました」 半眼になったウォルフガングが低い声で言う。 「それで、これから孫と街へ出かけようかと。自分の留守中、ミオ様に城をお願いしますと連絡に行ったところ……」 「ちょうど、同じ用件でウォルフを訪ねた私とバッタリ、廊下で遭遇した次第です」 ウォルフの後ろからひょこっと顔を出す、小柄な女性。侍女のミオである。 キュロス様は額に汗を垂らし、はははっと軽やかに笑った。 「そ、そうか。それはそれは……二人とも、責任感が強いというかなんというか、ご丁寧なことで……」 「お褒めいただき有難き光栄」 「で、それはそうとして旦那様。これはどういうことですか?」 ミオの青い瞳がギラリと煌めいた。 ひっ、と息を呑むキュロス様。 「あ、ああ、ええと」 「私に今日、休暇を取れと勧めたのは旦那様ですよね。ウォルフとツェリがいるから大丈夫だと言って強引に。……それでウォルフにも暇を出していたのは、一体どういうおつもりで」 キュロス様は血の気を引かせ、少しでもミオから距離を取るようにのけぞった。 「い、いや……あ……その」 侍従二人に睨まれて、キュロス様はゆっくりと席を立ち、じりじりと後ずさった。 「ええとそれは、その……ええと……あの」 じりじり逃げるキュロス様、じりじりと寄って行く執事達。 「それはその――ええと。――ごめん」 「ごめんで済んだら、執事は要りませんぞ!」 ウォルフガングの怒号が飛ぶ。そして始まる、長く厳しいお説教タイム――キュロス様は今度こそ震え上がり、きちんと、本気で謝った。 わたしはそんな三人を、クスクス笑って眺めていた。だって今回はわたし、なんにも不快な思いをしていないもの。 キュロス様ったら、馬鹿ね。侍従達を出し抜く画策なんてする必要ないのに。 わたしはもうすっかり彼に心を許している。わたしの髪や肌だって、彼ならばいつでも、好きなだけ触れることができる。わたしは委縮どころかむしろ嬉しくて、幸せな気持ちになって……さらにずっと、彼への想いが高まっていくだけなのに。 でも、そのことは教えずにおこう。 キュロス様がわたしを喜ばせるため頭を捻ってくださることが嬉しいし、次はどんな突拍子もないことをしてくれるのか、これからも楽しみにしているからね。
冬の四十五日目。その日を、ディルツ王国では『恋人達の日』と呼ぶ。 女性が意中の男性に贈り物をし、想いを伝える日だ。王都中央市場は女性客で溢れ、グラナド商会も繁忙期を迎える。そのため、俺もしばらくは城を留守にしがちであった。やっと暇が出来たのは、『恋人たちの日』の前夜。 夜勤の門番以外は侍従達も寝静まった時刻、俺は厨房に立っていた。 「――というわけで! 俺は、マリーに贈るお菓子を作るっ!」 「なんでそうなるのぉ」 隣に立つ、料理長のトッポが呆れたように呟いた。 「……なんでって、何が疑問なんだ?」 「だって、『恋人達の日』は女性が男性に告白する日でしょ。旦那様は男性、それも王族に次ぐ地位たる公爵令息、この国一番の大富豪グラナド商会の大旦那で、マリー様は婚約者。わざわざ手作りしなくたって――」 「どうでもいいだろそんなこと」 俺はあっさりと言い切った。 「立場もイベントも関係なく、俺はただ自分が嬉しかったことを、マリーにも体験させてあげたいだけなんだから」 昨年、俺はマリーから手作りのチョコレートを受け取った。普段は控えめで受け身がちな彼女が、照れながら差し出してきた小さな包み。嬉しかった。あの喜びを、マリーにも与えたい、お返しがしたい……そう思って当たり前じゃないか? そこに性別など関係ないだろう。 トッポは一応、俺が贈ること自体には納得してくれたらしい。しかし『手作り』という部分にはかなり難色を示していた。俺の手元を後ろから覗き込み、 「……旦那様、ほんとにだいじょぶ? お料理なんてほとんどしたことないでしょ」 「大丈夫大丈夫」 俺は笑顔で頷いた。頭についた、白い粉を叩き落としながら。 「材料は多めに用意している。あと三回くらいなら、小麦粉をひっくり返しても平気だ」 「……トッポ、お手伝いする?」 「うん。頼む。助かる。ありがとう」 俺は素直に礼を言った。 ……そう、トッポの言う通り、お菓子作りは思いのほか難しかった。レシピにはさも簡単そうに書かれているのに、実際やってみると極めて繊細、かつ重労働。 「慣れれば手抜きしていいところや、何を抜いてもだいじょぶってわかってくるんだけどねー。旦那様みたいなへたぴっぴは、レシピ絶対ね」 「……悪かったな、へたぴっぴで」 出来上がった黒い物体を手に持って、俺はトッポを振り向いた。 「これ、なんとか食べられる状態にできないだろうか?」 「うん、脱臭剤や畑の肥料にはなると思うよ!」 「……それは良かった」 それでも、諦めはしない。俺は再度材料を確認し、またイチから作りはじめる。 ……レシピ遵守、きっちり計量……強すぎず弱すぎず、手早く……。 きっちりと量った溶かしバターを、小麦粉に注ぎ、混ぜ込んでいく。 ……俺は今までお菓子なんて、出来上がった物しか見たことが無かった。自分で作ってみようなんて、考えたことも無かった。 「こんなに難しくて、大変なものなのだな……」 「もうお料理、嫌になっちゃった?」 俺の呟きに、トッポが言う。俺は首を振った。 「いいや。プロの料理人の技術、偉大さをしみじみと実感した。昨年手作りしてくれたマリーにも、感謝の思いと、愛おしさが増したな。時々こうして、自分で経験するべきだと強く思ったよ」 俺の言葉に、トッポは「うふふ」と楽しそうな声を漏らした。 ――それからも、大いに手間取りはしたが、トッポがついていてくれたおかげで、作業は順調に進み……。 「――できた!」 焼き上がったクッキーを前に、俺は一人、歓声を上げたのだった。 「マリー、『恋人達の日』のお菓子、作ってみたから食べてくれ!」 そう言って、俺は両手に持った箱を差し出した。 マリーはパチクリ、瞬きをする。とりあえず箱を受け取ってから、しばらく俺の顔をまじまじと見つめていた。結構な時間を要してから、やっと「ええっ!」と声を上げた。 「キュロス様が? お菓子作りを……わたしのために⁉」 マリーは声を震わせ、感動しているようだった。その目に涙が浮かんだのを見て、俺は慌てた。 「そ、そんなに喜ばれると困る。箱を開けてみてくれ。きっと笑ってしまうから」 「笑ってしまう……?」 マリーは首を傾げ、白い箱を見下ろす。両手でなければ持てないほどの大きな箱だ。俺が蓋を取ってやると、マリーは中を覗き込み、そして再び、首を傾げる。 「クッキー……が。ひとつ、だけ?」 「箱に対し、明らかに不釣り合いな量だろ。ちなみに箱は事前に用意をしていた」 「……えっと。それってつまりキュロス様、たくさん失敗を……」 「うんそう。昨夜は徹夜して、この箱を五つ満杯にできるくらい挑戦したのだがな。……生き残ったのはこれだけだったんだ」 「えっ、徹夜……!」 マリーの顔が曇る。俺は笑って、マリーを抱きよせた。安心させるように頭を撫でてから、優しく囁く。 「笑ってくれ。笑顔が見たい」 「は、はい……ふ、ふふ。ふふふっ……」 まだぎこちない笑顔。俺はクッキーを摘まみ取り、マリーの口に入れてやった。たったひとつだけのクッキーを、マリーは目を閉じゆっくりと咀嚼した。大切に大切に味わって……。 「……ああ……とっても美味しいです」 目に涙を浮かべたまま、満面の笑みを浮かべてくれた。 クッキーを食べ終えたマリーは、空き箱をデスクに置きに行き、代わりに小箱を持ってきた。可愛らしくラッピングされたそれを、俺の手のひらにちょこんと置く。 「わたしも用意していました。一昨日、キュロス様が留守の間に厨房を借りて」 包みを開けると、中には小さなチョコレートがたくさん入っていた。 「あ、ありがとう……」 俺は礼を言ってから、マリーの作ったチョコを一粒摘まんで、食べてみた。 ……美味い。 マリーの手作りチョコは、既製品に遜色ないほどに十分、美味かった。しかも俺がちょうど好む甘さ加減で、彼女の調理技術と、食べる人への思いやりが感じられる。自分がさんざん失敗した後だからこそよく分かる。俺は苦笑した。 「今日はつくづく、自分の甘さを実感したよ。普段、何も考えずに出された物を食べていたのが恥ずかしい。料理人や職人、君への感謝と敬意で胸がいっぱいだ」 肩を落としてそう呟くと、マリーは、ふふっと笑い声を漏らした。 「そういうの、キュロス様のすごいところだと思います」 「……ん? 何がだ」 「しかもそれを自覚してないところ。当たり前にできるところ」 「だから、何の話だ?」 「そんなあなたが、わたしは大好きだっていうお話です」 クスクス笑いながら、踊るように身を翻して言うマリー。 「あなたの恋人になれて、わたしは幸せです」 くるくる回り、鼻歌まで歌って部屋の中を舞っている。心なしか頬まで赤い。 ……はて? クッキーの材料に、酒は入っていなかったはずだが。 ……とにかく、彼女が楽しそうで何よりだ。なんであれ喜んでくれたなら、それでいい。 俺は頭に小さな疑問符を浮かべながらも、踊る彼女に手を差し伸べた。 「どうせ踊るのならば、ふたりで一緒に」 彼女は微笑み、俺の手を取った。 冬の四十五日目、ディルツ王国にとってほんの少しだけ特別な日。 俺とマリーはほんの少しだけ特別な、だがいつもと変わらない時間を過ごす。 これといった理由も意味もなく、笑顔で愛を囁き、手を取り合って、静かに踊る。きっと来年も再来年も、似たような日を過ごすだろうと思いながら。


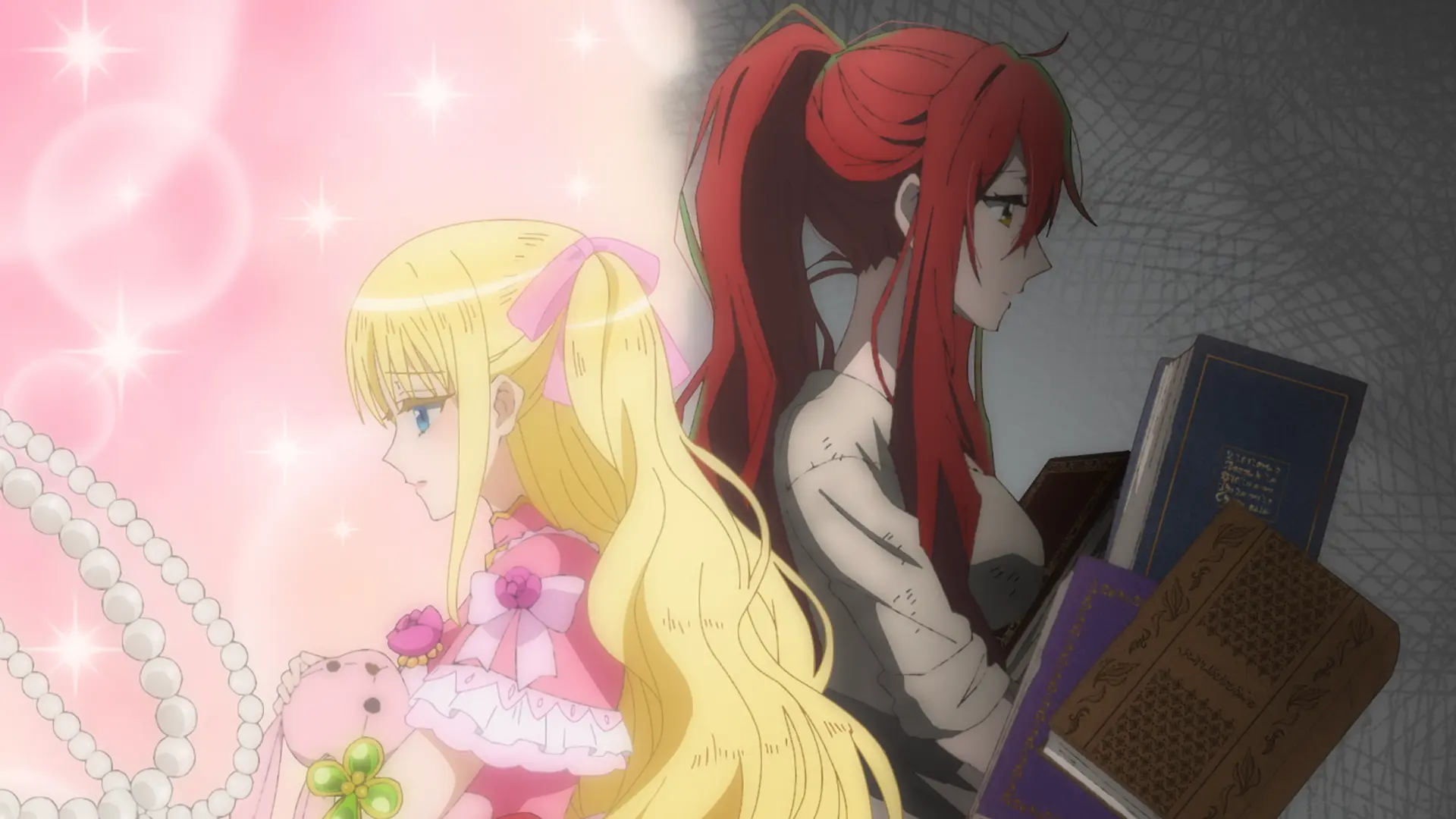







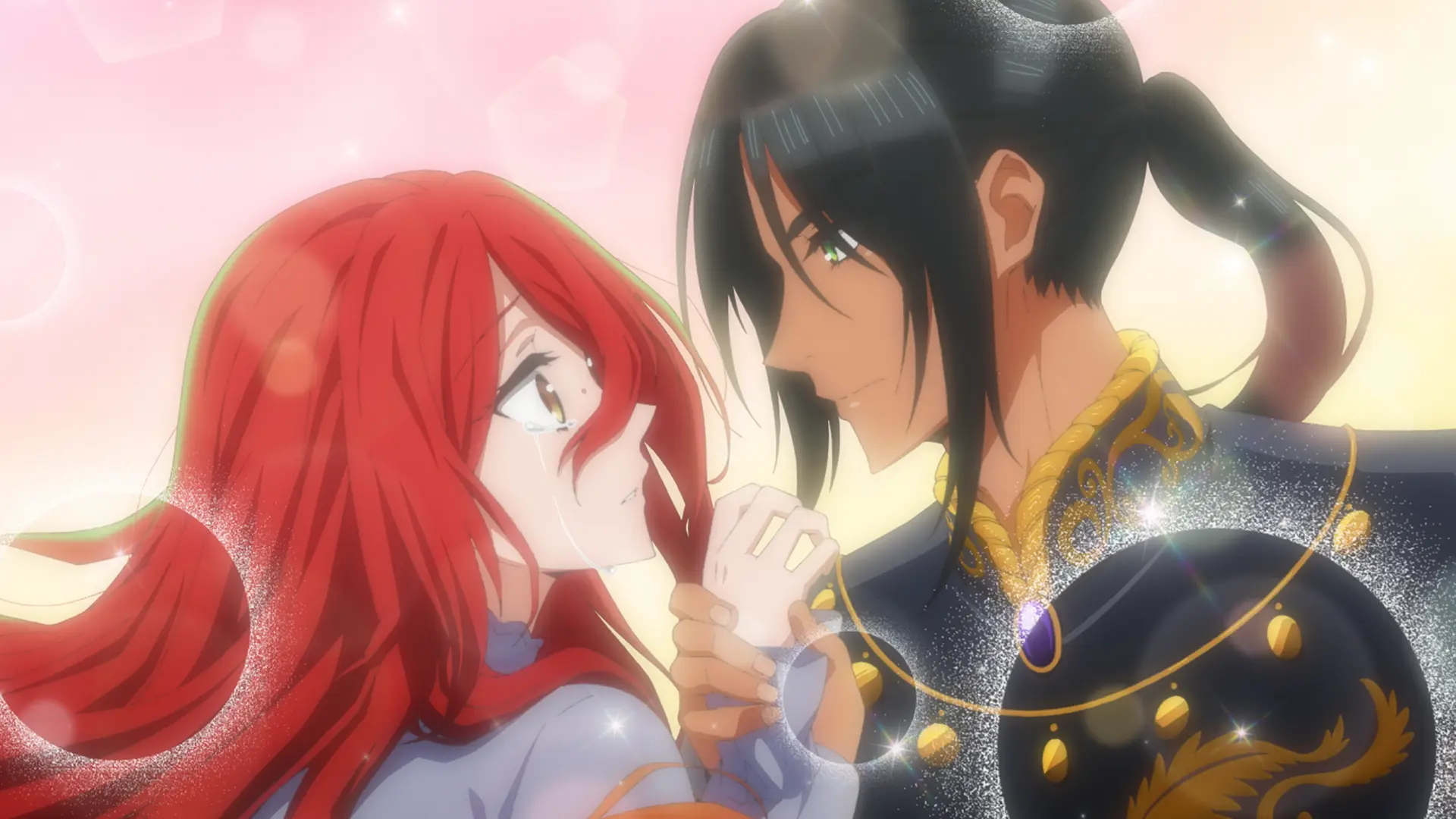

強く美しく成長してきたずたぼろ令嬢の物語は、月が夜空を照らすように、心を優しくあたためてくれました。 みんなで歩んできた絆が、どうしようもなく愛おしいです。 マリーの瞳に映る、いっぱいの溺愛と色とりどりの花束を、一緒に見届けてください。 宜しくお願いいたします。
とうとう待ちに待った最終回ですね。 グレゴールとエルヴィラの秘密とは…!? 強く気高く両親と対峙するマリーの振る舞いに大注目です! はたして大団円を迎えられるのでしょうか!? お楽しみいただけたら嬉しいです!